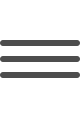田宮督夫氏 追悼記事
『ツインスターを創った男』
パンツァーグラフ!12
完全保存版 タミヤ1/35 ミリタリーミニチュア40周年記念号
2008年4月14日発売
『ツインスターを創った男』
パンツァーグラフ!12
完全保存版 タミヤ1/35 ミリタリーミニチュア40周年記念号
2008年4月14日発売
インタビュー / 編集:金子辰也
撮影:奈良岡忠
写真:モデルアート

撮影:奈良岡忠
写真:モデルアート

今や、日本というよりも世界中の模型ファンを魅了し続けるツインスター。今から48年前の1960年、兄俊作が満身の力で作り上げたタミヤ最初のプラモデル。そして、そのパッケージには弟督夫が創った初代ツインスターが印刷されていた。そのツインスターから放たれる光はまだよわよわしいが、未来に向けてどこまでもまっすぐにのびて行くかのように徐々に輝きを益していくのであった・・・。

●メモ
今年の3月20日過ぎ、もう何年振りだろうか地下鉄青山1丁目近くの静かなマンションに、ある方を取材で訪ねた。今ではご自身の個人デザイン事務所とアトリエを兼ねている。平日は、ほぼ毎日自宅から通われ、齢70を越えられた現在も立体とも平面とも言える厚い紙のボードを細く切り出した物をカラフルに彩色し、更にデザインに合わせながらカットしてひとつずつ丹念に組み合わせたオリジナル作品を創られていると言う。
ちょうど3年前の2005年には六本木のアクシスで個展も開催された。オープニング初日の夜には軽いパーティーも開かれ、多くの方々が集まり盛況であった事を思い出す。すでに、その段階でほとんどの作品には売約済みのステッカーが貼られていた。そこには、ちょうど海外から帰国されたばかりの兄、田宮俊作社長もお見えになり、しばらくそこで立ち話をした記憶がある。
今回は、事前に当然の事ながら本誌「タミヤ1/35MMミリタリーミニチュアシリーズ40周年記念号」にて、タミヤに於ける田宮督夫氏のやってこられた38年間に渡っての仕事について伺う旨の取材である事を伝えていた。カメラマンや録音機材の準備も整いインタビュー取材がスタートした。
そして、最初に督夫氏から「ちょっと、メモを作っておいたので…」と、角をホッチキスで綴じたA4サイズの用紙を渡された。そこには、No.1から20まで一枚ずつ項目ごとにご自身のこれまでのタミヤに於ける38年間を中心に、前後・東京芸大時代から今日まで約50数年間の軌跡が手書きでびっしりと書かれたメモのコピーであった。

■そもそもの出会い
私が、青山の今とは別のマンションにあった田宮督夫さんの事務所(普段、タミヤの東京事務所と呼んでいた)を最初に訪れたのは今から31年前の1977年であった。おそらく、その年の前半か前年の末に東京で開催された「AFVの会」に初めて参加し、その時の作品を主催者であった当時ミリタリー模型ファンのあこがれであった〈カンプグルッペジーベン〉代表・十川俊一郎氏に認めて頂き、それが縁でカンプに入会。
そして、それから行動をともにする中で、十川さんがある日、「田宮さんを紹介するので」と、何人かのメンバーと青山のタミヤ東京事務所へ初めて連れて行ってもらい、ご挨拶したのが始まりであった。そして、その年の秋のホビーショー用にカンプメンバーの新人デビュー作として製作したのが、今回本誌・永島健司氏とも縁となった「羊飼い」のジオラマであった。
そして、その後はタミヤのMMの新製品が出ると、時々青山の田宮さんから連絡があり、その都度事務所に出向き、まだ発売前のテストショットを頂き『ホビージャパン』誌に於いてキットレビューとして作例を作るなどしていた。
しかし、実は縁とは不思議なもので、田宮督夫さんとは更にさかのぼって、まだ私がデザインの専門学校である桑沢デザイン研究所の学生で通っていた頃、3年のグラフィックデザイン研究課に「田宮模型が実家の田宮督夫という先生が教えに来ている」と友人から聞いていたのである。
しかし当時は、1年休学して半年バイトで資金を稼ぎ、半年パリをベースにロンドンやスペインを回っていたり、帰国復学後も青山のデザイン事務所でのアルバイトや、デート、学校の課題に追われていたりで、ちょうど高校入学くらいからその後学校を卒業、結婚、社会人になるまで模型とは少し距離を置いていた頃であった。
そんな訳で、残念な事に当時いち学生としてご挨拶くらいはしたかもしれないが、結局直接授業を受ける事は無かった。しかし、後に人を通じて督夫さんが私の事を「教え子のひとりだ」と言っていたと間接的に聞き、嬉しく思ったものである。そういう訳でもないのだが、当時から現在まで田宮督夫さんのことはいつも「先生」とお呼びしてしまう。
■静岡から東京芸大へ
という訳で、督夫先生は俊作社長とは3歳年下の弟で、田宮家の三男であった。1937年(昭和12年)12月30日生まれ。お話の中でも、いつも「自分の誕生日は大掃除だった」とこぼしていらした。
子供の頃は大工さんになりたいと思い、色々と工作する事が好きな少年だったようである。高校時代は地元の進学校に進み、その後芸大受験の志望動機が「中学生時代に美術の先生に『おまえは芸大に行け!』と言われた事」と「学科が一番少なくデッサンや絵の受験勉強をする方が良かったから」との事。
結局、現役挑戦は失敗し、翌年一浪として再度受験する為に母親を説得して東京へ。池袋に下宿していた当時まだ早稲田の学生であった兄・俊作氏を頼って転がり込む。そして芸大受験準備の為に阿佐ヶ谷美術学園へ通い、お腹をすかせながら木炭デッサン用の食パンをお腹の足しに日々受験勉強に励んだとの事。
また、再受験で東京へ旅立つときには髪の毛を丸刈りにしたこと、そして無事芸大に入った後もお金がなかったので、友達が出来ると喫茶店などへ行く事となる為、その出費が負担になるので、当初は余り人とは話さない様に心がけていた。おかげで最初のうちは「変わった人だ」と周囲から思われていたようである。
督夫先生 / 浪人して東京行く時は坊主にして、「絶対に入らなければ」と思っていて、友達と話すと何かと喫茶店へ行くからお金が掛かるし、友達とは話さなかった(笑)。「あの人全然お話しない人だ」っていうのは暫くありましたよ。
学校入ってからは芸大の寮に行きまして、そこは寮長をやると食費が800円だったか払えばいいだけで、寮長に立候補したんですけど、公約がネズミ退治なんですよね。ネズミ退治の薬を貰ってきて置いて退治したってだけの話なんですけど。
その時は音校の寮と一緒でしたから、30歳くらいの男性がひとり立候補して、私は「早くお嫁さん貰いたい」と言ってましたけど(笑)。ただ、寝ていると昔のおが屑を固めたような壁で、すき間から星が見えるんですよね。隣りでタバコ吸うと煙が入ってくるとかして、本当にひどい寮でしたね。そこに3年間居ましたけどね。
でも、「何かアルバイトやらないか」って事で、新宿の伊勢丹の新宿駅寄りに「いさみ屋さん」って言う婦人用品を売ってる店があって、銀座にも松坂屋と松屋の間にいさみ屋さんがあったんですよね。あと紳士用品店があって、そこで看板を描くんですよね。
で、どう見てもそこでそういう事やってた人の方が上手いんですよね。ファッション物なんて描けないじゃないですか。「秋の婦人服揃う」とか描くんですけど、お金は良かったし、夜行くんですけど晩ご飯を出してもらえるんで、食べさせてもらっていましたね。
ただ一番困ったのは、新宿で描いて銀座に看板を納めてこいって時に、その看板は天井から吊るすようなやつで180cmぐらいあったんですね。で「これじゃ電車には乗れません」って言ったら「いや、自転車で行くんだ」って言われて、三宅坂の所なんかだと看板をちょっと動かす度に風に煽られましたね。一番嫌だったのは銀座四丁目の交差点で信号待ってる時ですね。誰かに見られてるんじゃないかって(笑)。

■ツインスターの誕生
そんな東京での貧乏学生生活を続ける中、静岡の兄・俊作氏から、まだ芸大の1年生だった督夫氏の所へ「本格的なタミヤのロゴマークを製作して欲しい」との依頼が…。
金子 / 最初のタミヤのロゴマークとなった地球儀のデザインは督夫先生だったんですか。
督夫先生 / あのマークについては私は全然タッチしていませんね。
金子 / それでは、俊作社長がお作りになられたんでしょうか。
督夫先生 / いや、何かその辺にある物から「これにしよう」っていう程度の物でしたね。
金子 / それで、今に至る最初の初代ツインスターマークは…。
督夫先生 / ちょうど昭和32年(1957年)、大学1年生の時プラモデルが入ってきて、やはり今までの木製模型とは違う物なので新しいマークをということで、その時に星のマークを考えたんですけども、当時はまだ1年生で印刷とかの事について余り詳しく知らなかったので、黄色を使ったんですけど、凄く使いにくいという事で、スロットレーシングカーの白いパッケージの時に作り直しました。
星のイメージについては、昔子供の頃〈三星絵具〉というのがあったんですね。それを買ってもらったのが嬉しくて、それが何しろ子供心に凄く格好良かったんです。それが、どこかで星をモチーフにデザインをするきっかけになったのだと思います。それと「タミヤ」っていうカタカナのやつは社長から頼まれて作ったんですが、「タミヤ」って読んでくれなくて「タニャ」って随分呼ばれましたけどね(笑)。
※最初のツインスターマークは通説では1960年(昭和35年)に誕生したとされるが、ここで督夫先生が芸大の1年生の時に俊作社長に頼まれて製作したとしたら、製作年度は1957年(昭和32年)という事となり、実際に製品に印刷されて1960年に世に出たとすると、その間の3年あまり使用されずに寝かされていたという事となる。また、〈三星絵具〉についてはその存在を編集部では確認したが、画像については現在未確認である。どなたかご存知の方がいらしたら是非、編集部まで情報を提供頂きたい。(編集部)

■大手百貨店宣伝部門へ
現在は既に無くなって形を替えているが、当時広告業界の最高の賞として「日宣美」と呼ばれ、多くの有名デザイナーを輩出してきた栄誉があった。そこに、1959年(昭和34年)まだ芸大の大学3年生であった督夫氏はパッケージデザインで応募し、見事受賞。その類まれな才能の片鱗を表し始めている。
そして1961年(昭和36年)、高島屋の宣伝製作部門「宣研」に入社。その後も新宿京王百貨店の宣伝部に移籍し、立ち上げから関わる。その間も百貨店の屋外広告(ネオンサインデザイン)などでADC賞を受賞。
その間もタミヤの仕事を手伝い、またデザイン専門学校などでも教鞭をとるなど超多忙を極める。そして1967年、京王百貨店を退社しフリーとなり、本格的にタミヤの仕事に関わって行くようになるのであった。
金子 / 先生がパッケージを選ばれて出された、というのは元々芸大にいた時からパッケージをやろうとか思っていらっしゃったんですか?
督夫先生 / 僕は元々デッサンとか写生っていうのは凄い下手なんですよ。だから僕が一番ビリで試験に受かってると思うんですよね。大工さんとか立体の物を作る方が好きだったんですね。それで、パッケージで賞を取った人はいなかったですね。だから、それは穴だったって事です。
それで「良いチャンスが来たな」と思い応募したんですね。そしたら本当にまぐれ当たりで。或る方が盛んに勧めてくれてたみたいですけど。朝日新聞では「斬新性が無い」と批評がありましたけどね。
それで夏休み入ってすぐ高島屋で展覧会をしたんですけども、夏休みに友達と北海道一周やろうって約束していて、「入った!」って大喜びでそのまま北海道行っちゃって。だから、そういうところも凄いのんきで、いろいろな出版社とかからの問い合わせが寮の方にあったらしいのですけど「どこ行ったか分からない」と(笑)。そんな程度です。
だからそういうものを取ったら、その後それなりに仕事を続けていかなきゃならない、作品を発表していかなければならない、という気持ちが無かったんですよね。ただ、日宣美には「次も入ろう」と思っていて、2回続けて入ったんですね。

督夫先生 / 私は高島屋の後に京王百貨店ができるという事で、高島屋の宣伝部の方の半分が京王百貨店の方に移りました。その時に「百貨店の開店に立ち会えれば面白いな」という事で私も移籍しました。
それと同時にその頃「すいどーばた(すいどーばた美術学園)」や「桑沢(桑沢デザイン研究所)」へも行ったりしてたんですが、会社からは当然ながら「お前はいつ働いてるんだ?」って言われた事がありましたね。
それと今の社長がそのころは静岡で、組み立て説明図から全てデザイン・レイアウトまでしていて、パッケージも最初の頃はやってたんですけど、どうしても上手く行かないんで「手伝ってくれ」と。
私自身が百貨店でやっている仕事っていうのも、「自分がこれからやり続けていく仕事としてこんな事やっていていいのか」という事で多少色々と考えていた部分もあったんですよね。
そこで、草刈順さんというその世界では有名なデザイナーの方が当時高島屋の時の上司で「やっぱりちゃんとした(有名企業)所でやった方が良いんじゃないか」とか言われたんですけど、段々静岡の方も輸出だとか何だとかって事で「ちゃんとした物を造らなきゃいけない」という方向になってきて、「それなら、まだ小さい会社だけどタミヤの仕事にひとつ掛けてみようかな」という気持ちでやりだした訳ですよ。
自分がやってる間に知名度を上げたり人気を上げるのは無理かなという気持ちでしたね。だから凄い必死だったんです。タミヤの仕事でどんな事でもマイナスになるような事とか、手抜きをしてはだめだとか、というのが自分の中には凄くありましたから。
金子 / 今やタミヤの代名詞のように言われますが、あのホワイトパッケージと呼ばれているデザインはどのようにして生まれたのでしょうか。
督夫先生 / スロットレーシングの箱から始まったんですけど、背景の無い車だけの絵って事ではコックスの箱とか、あれは今思い出すと上面図だとか、とても格好良かったんですね。その影響もあって「何とか車だけの絵」という事で、その時日本デザインセンターに河上さんという方がいまして、その人が描いてくれるって言うのでお願いしたのが始まりなんですけど。
この白い箱に車を入れて、袋とか鞄にも入れず白箱のままスロットレーシングの競技へ持って行くのが凄くファッションだったんですよ。当時はホッチキスでサイドを留める箱が主流でしたから、アメリカのように薄紙に印刷してから厚紙に貼るという「貼り箱形式」が何とかできないかって。でもそれが中々できなくて、唯一そういうカタチに近い物は折り箱でできていたワイシャツの白い箱だったんです。
で、その見積もりをとったんですけど凄い高いんですね。ですから一番苦労したのは印刷の技術とか、箱なんかも「絶対ちゃんとした物を造っていかなくちゃいけない」という事でした。しかし印刷屋の方も非常にのんきでしたから苦労しましたね。
それで何とか採用する事が出来て、その後のワールドタンクシリーズも白箱でやったんですけど。
金子 / ありましたね。1/50のクルセイダーは非常に良く憶えています。
督夫先生 / それから1/35の戦車で一番最初の白箱は、チーフテンですね。
金子 / あと僕なんかがよく憶えてるのは、キングタイガーとハンティングタイガーが出た時に、白箱で凄くモダンと言うか、オシャレだな〜って。
督夫先生 / それでちょうどですね、小松崎茂さんのところに上田信ちゃんが弟子で入ってて、大西君はそこへ入りたいって言ってたんですけど、小松崎先生がもう弟子はとらないと言って、小松崎さんと当時うちの長倉部長とは遠い親戚で、「こういうのがいるけどお前んとこで使え」と言う事で来たのが大西(将美)君だったんですよね。
それで来て絵を描くと言っても何とか絵を教えなければいけないと言う事で、フェーマース・アート・スクールのテキストを買って、それを教科書にして一番最初からやりだしたんですね。月曜日に仕事終わってから大西とか島村とか松村とかいるんですけど、そういうのに教えていましたね。
大西君にしても絵は描けるんですけど、基本的にそういう事はやったことがないから「凄くやりたい」という話でやりだして。私もすいどーばた学園という美大系の予備校に教えに行ってた事もありますし、新設でデザイン課を作るという事でお手伝いをした事がありましたので、教える事はある程度できた訳ですね。
それで大西君みたいに基本的に描ける人は良いんですけど、あと何人か必要だと言う事で工業高校から入って来て少し絵が好きだという人達に教えていったんですけど、どうしても製品がブームになってくると新製品開発のテンポが早くなりますので絵が間に合わなくなってきます。
ですから高荷先生とか小松崎先生の役割を分散して間に合わせたんですけど、やはり半年以上経っても出来上がってこない絵もありましたしね。あんまり催促すると怒られるし。でも平野さんのが一番凄かったですね。
金子 / M42ダスター。
督夫先生 / あれは随分と掛かりましたね。で、上がってきたら今度は箱の縦横比率と全然合わなくて、仕方なく途中でつなぎ合わせて線が入っているものもあるかもしれませんね(笑)。
で、最初にMMシリーズではないですがチーフテンを描いて、次にMMシリーズのNo.001の戦車兵セットの箱絵を大西君が描きましたね。途中で大西君と福村君は独立していって、その時はどうなるのかと思いました。しかし外で描いてもらう事で助かったんですけど。
金子 / MMシリーズ001番の3体の戦車兵キットのパッケージを大西先生が描かれて、その後にIII号戦車とIII突に付いていた戦車兵が一体加わり4体セットになりましたが、4体セットのパッケージの4人目は大西さんが描かれたのでなくて、たぶん島村さんが大西先生の画風に似せてお描きになったのだと。だから、あれは要するに大西さんと島村さんの合作だという事を松井康真さんから聞いて、確かにそう言われて良く見るとニュアンスがちょっと違うんですよね。
で、この前大西さんにお電話して話している時に、ちょっとその事を聞いてみたんですけど「確かに僕は描いてない、島村先生なんじゃないかな」とおっしゃっていました。
督夫先生 / 人物を描くのは、大西君みたいに慣れてればいいけど…。

「日本のロゴ」のキャプション
もはや、模型の世界を越えて今やCanonやYAMAHA と同様に
日本を代表するブランドマークとなったタミヤのツインスター。
『日本のロゴ」成美堂出版
督夫先生 / それから、組み立て説明図には作り方だけじゃなくて実車の説明を入れるという事をちゃんとやっていこうと言う事で私がやりだしたんですけど。ただ段々「キットを買ってきて、箱開けて、組み立て説明図見て、パーツ見て、それで終わり」という、それで十分なモデラーをどうするかという事は解決できなかったですね。
後にF社の1/76とB社の1/48ミリタリーキットが登場して、情景作りというのはそっちの方が絶対小さいし条件が良いと思った訳ですね。それで「どちらにしても情景を作ろう」という展開をして、B社とF社より有利に立つ方法として1/35のどこに有利性があるかと考えると、やはりフィギュアなんですね。あの大きさというのが作りやすいし改造しやすいという部分をPRしよう、となったのです。
それで始めたのが「人形改造コンテスト」だったんです。ですからそれはそれで成功したと思うんですけど、それによって人形の改造を専門にする人達が出てきたのは計算外でしたね(笑)。フィギュア1体で何ヶ月も楽しめてしまう。
それから、その頃はまだ「ジオラマ」という言葉を知りませんでした。で、「なんて言ったらいいのかな」と。それで色々話し合った結果「情景」という言葉を使うように決めたんですけど、B社が「ジオラマ」という言葉を使い始めた時はまずいなと思いましたね。でも「情景」という言葉は結構定着してくれたのかなと、その時は思いましたけどね。
金子 / 「ジオラマ」という言葉は既に明治時代に外来語で入ってきて日本語化されてますけど、最近だと英語風に言ってみたりとか、いろいろ各雑誌社で呼び方が違っていて、そういう意味でタミヤさん的には中立を守って「あえてジオラマと言わずに情景という言い方をしているのかな」と僕達は思っていました。
督夫先生 / ですから「情景」という言葉をあらゆる印刷物に入れて行くという事でやってきましたけど、でもそんなに言葉としては悪くはないのではないかなと。
金子 / そうですね。非常に良いと思いますね。やっぱり漢字の方が伝わるものも多いですよね。
督夫先生 / そうですね。それはありますね。
昔モノグラムの工場見学というのがありまして、何か会社の方として色々あったのか、その辺はちょっと分からなかったんですけど、タミヤにボスさんという方がいて、その方と一緒に工場見学してる時、通路にモノグラムの原画が飾ってあったんですね。
僕はタミヤでは非常に大きい原画を描いてもらい、その方が縮小を掛けて印刷効果が良いですね。そうしたら、本当に小さいんですよね。でも「やっぱり手慣れた絵だな」という事で、日本の色んな物と比べてアメリカのグラフィックっていうのをわざわざ見せつけられた感じがしましたけどね。

督夫先生 / カンプの十川さんから「模型をもっと一般に理解してもらいたい」という話が出て、「東急ハンズの模型屋さんで展示してもらえないかな」という話になり、早速営業から問い合わせしたら、たまたま東急ハンズの上にギャラリーがあって、そこを閉めてしまうようで空いてるから「そこを使ったらどうだ」と言われ、使わせてもらったのがタミヤモデラーズギャラリーの始まりなんですね。
渋谷の駅から東急ハンズまで、行列という程ではないのですけど「これはモデラーズギャラリーに行く人だな」という流れというか列が分かりましたね。
それまでは百貨店でやらせて欲しいと申請しても「机の上に白い布敷いてその上に戦車とか船並べるなんて百貨店では出来ない」と言う話だったのですが、東急ハンズでやった実績のおかげで、その後札幌そごうでOKが出て「これだったらやっても良い」という事になって、それがギャラリーの1回目だったんですけど。それは嬉しかったですよね。
それから大阪、名古屋、福岡、新潟と全国的に開催していった訳ですね。ですから、ギャラリーのスタートっていうのは十川さんのアドバイスがきっかけになっています。
督夫先生 / 1967年の1月に『タミヤニュース』の第1号を隔月で発行しました。それで、その年の8月に『ジュニアニュース』を出しました。
金子 / ちょっとお聞きしてもよろしいですか?
督夫先生 / はい。
金子 / 松井さんとよく話しているのですが、この前もちょっと俊作社長にお聞きしたんですけども、『タミヤニュース』の第1号が1967年の1月号という形になっていて、今まで色々な出版物とか記録を見ると「1月号」と書かれているので、1967年の1月発行という風に言われているんですけども、どうなんでしょうか?
督夫先生 / 早め早めに原稿作って、そういう物って発売を予定した日より前に発行するという慣例がありますから、それは前の年だと思います。
金子 / そうすると、やはり1966年の12月なり、11月の可能性があると。
督夫先生 / そういう事ですね。


それと今の社長がそのころは静岡で、組み立て説明図から全てデザイン・レイアウトまでしていて、パッケージも最初の頃はやってたんですけど、どうしても上手く行かないんで「手伝ってくれ」と。
私自身が百貨店でやっている仕事っていうのも、「自分がこれからやり続けていく仕事としてこんな事やっていていいのか」という事で多少色々と考えていた部分もあったんですよね。
そこで、草刈順さんというその世界では有名なデザイナーの方が当時高島屋の時の上司で「やっぱりちゃんとした(有名企業)所でやった方が良いんじゃないか」とか言われたんですけど、段々静岡の方も輸出だとか何だとかって事で「ちゃんとした物を造らなきゃいけない」という方向になってきて、「それなら、まだ小さい会社だけどタミヤの仕事にひとつ掛けてみようかな」という気持ちでやりだした訳ですよ。
自分がやってる間に知名度を上げたり人気を上げるのは無理かなという気持ちでしたね。だから凄い必死だったんです。タミヤの仕事でどんな事でもマイナスになるような事とか、手抜きをしてはだめだとか、というのが自分の中には凄くありましたから。
金子 / 今やタミヤの代名詞のように言われますが、あのホワイトパッケージと呼ばれているデザインはどのようにして生まれたのでしょうか。
督夫先生 / スロットレーシングの箱から始まったんですけど、背景の無い車だけの絵って事ではコックスの箱とか、あれは今思い出すと上面図だとか、とても格好良かったんですね。その影響もあって「何とか車だけの絵」という事で、その時日本デザインセンターに河上さんという方がいまして、その人が描いてくれるって言うのでお願いしたのが始まりなんですけど。
この白い箱に車を入れて、袋とか鞄にも入れず白箱のままスロットレーシングの競技へ持って行くのが凄くファッションだったんですよ。当時はホッチキスでサイドを留める箱が主流でしたから、アメリカのように薄紙に印刷してから厚紙に貼るという「貼り箱形式」が何とかできないかって。でもそれが中々できなくて、唯一そういうカタチに近い物は折り箱でできていたワイシャツの白い箱だったんです。
で、その見積もりをとったんですけど凄い高いんですね。ですから一番苦労したのは印刷の技術とか、箱なんかも「絶対ちゃんとした物を造っていかなくちゃいけない」という事でした。しかし印刷屋の方も非常にのんきでしたから苦労しましたね。
それで何とか採用する事が出来て、その後のワールドタンクシリーズも白箱でやったんですけど。
金子 / ありましたね。1/50のクルセイダーは非常に良く憶えています。
督夫先生 / それから1/35の戦車で一番最初の白箱は、チーフテンですね。
金子 / あと僕なんかがよく憶えてるのは、キングタイガーとハンティングタイガーが出た時に、白箱で凄くモダンと言うか、オシャレだな〜って。
督夫先生 / それでちょうどですね、小松崎茂さんのところに上田信ちゃんが弟子で入ってて、大西君はそこへ入りたいって言ってたんですけど、小松崎先生がもう弟子はとらないと言って、小松崎さんと当時うちの長倉部長とは遠い親戚で、「こういうのがいるけどお前んとこで使え」と言う事で来たのが大西(将美)君だったんですよね。
それで来て絵を描くと言っても何とか絵を教えなければいけないと言う事で、フェーマース・アート・スクールのテキストを買って、それを教科書にして一番最初からやりだしたんですね。月曜日に仕事終わってから大西とか島村とか松村とかいるんですけど、そういうのに教えていましたね。
大西君にしても絵は描けるんですけど、基本的にそういう事はやったことがないから「凄くやりたい」という話でやりだして。私もすいどーばた学園という美大系の予備校に教えに行ってた事もありますし、新設でデザイン課を作るという事でお手伝いをした事がありましたので、教える事はある程度できた訳ですね。
それで大西君みたいに基本的に描ける人は良いんですけど、あと何人か必要だと言う事で工業高校から入って来て少し絵が好きだという人達に教えていったんですけど、どうしても製品がブームになってくると新製品開発のテンポが早くなりますので絵が間に合わなくなってきます。
ですから高荷先生とか小松崎先生の役割を分散して間に合わせたんですけど、やはり半年以上経っても出来上がってこない絵もありましたしね。あんまり催促すると怒られるし。でも平野さんのが一番凄かったですね。
金子 / M42ダスター。
督夫先生 / あれは随分と掛かりましたね。で、上がってきたら今度は箱の縦横比率と全然合わなくて、仕方なく途中でつなぎ合わせて線が入っているものもあるかもしれませんね(笑)。
で、最初にMMシリーズではないですがチーフテンを描いて、次にMMシリーズのNo.001の戦車兵セットの箱絵を大西君が描きましたね。途中で大西君と福村君は独立していって、その時はどうなるのかと思いました。しかし外で描いてもらう事で助かったんですけど。
金子 / MMシリーズ001番の3体の戦車兵キットのパッケージを大西先生が描かれて、その後にIII号戦車とIII突に付いていた戦車兵が一体加わり4体セットになりましたが、4体セットのパッケージの4人目は大西さんが描かれたのでなくて、たぶん島村さんが大西先生の画風に似せてお描きになったのだと。だから、あれは要するに大西さんと島村さんの合作だという事を松井康真さんから聞いて、確かにそう言われて良く見るとニュアンスがちょっと違うんですよね。
で、この前大西さんにお電話して話している時に、ちょっとその事を聞いてみたんですけど「確かに僕は描いてない、島村先生なんじゃないかな」とおっしゃっていました。
督夫先生 / 人物を描くのは、大西君みたいに慣れてればいいけど…。

「日本のロゴ」のキャプション
もはや、模型の世界を越えて今やCanonやYAMAHA と同様に
日本を代表するブランドマークとなったタミヤのツインスター。
『日本のロゴ」成美堂出版
督夫先生 / それから、組み立て説明図には作り方だけじゃなくて実車の説明を入れるという事をちゃんとやっていこうと言う事で私がやりだしたんですけど。ただ段々「キットを買ってきて、箱開けて、組み立て説明図見て、パーツ見て、それで終わり」という、それで十分なモデラーをどうするかという事は解決できなかったですね。
後にF社の1/76とB社の1/48ミリタリーキットが登場して、情景作りというのはそっちの方が絶対小さいし条件が良いと思った訳ですね。それで「どちらにしても情景を作ろう」という展開をして、B社とF社より有利に立つ方法として1/35のどこに有利性があるかと考えると、やはりフィギュアなんですね。あの大きさというのが作りやすいし改造しやすいという部分をPRしよう、となったのです。
それで始めたのが「人形改造コンテスト」だったんです。ですからそれはそれで成功したと思うんですけど、それによって人形の改造を専門にする人達が出てきたのは計算外でしたね(笑)。フィギュア1体で何ヶ月も楽しめてしまう。
それから、その頃はまだ「ジオラマ」という言葉を知りませんでした。で、「なんて言ったらいいのかな」と。それで色々話し合った結果「情景」という言葉を使うように決めたんですけど、B社が「ジオラマ」という言葉を使い始めた時はまずいなと思いましたね。でも「情景」という言葉は結構定着してくれたのかなと、その時は思いましたけどね。
金子 / 「ジオラマ」という言葉は既に明治時代に外来語で入ってきて日本語化されてますけど、最近だと英語風に言ってみたりとか、いろいろ各雑誌社で呼び方が違っていて、そういう意味でタミヤさん的には中立を守って「あえてジオラマと言わずに情景という言い方をしているのかな」と僕達は思っていました。
督夫先生 / ですから「情景」という言葉をあらゆる印刷物に入れて行くという事でやってきましたけど、でもそんなに言葉としては悪くはないのではないかなと。
金子 / そうですね。非常に良いと思いますね。やっぱり漢字の方が伝わるものも多いですよね。
督夫先生 / そうですね。それはありますね。
昔モノグラムの工場見学というのがありまして、何か会社の方として色々あったのか、その辺はちょっと分からなかったんですけど、タミヤにボスさんという方がいて、その方と一緒に工場見学してる時、通路にモノグラムの原画が飾ってあったんですね。
僕はタミヤでは非常に大きい原画を描いてもらい、その方が縮小を掛けて印刷効果が良いですね。そうしたら、本当に小さいんですよね。でも「やっぱり手慣れた絵だな」という事で、日本の色んな物と比べてアメリカのグラフィックっていうのをわざわざ見せつけられた感じがしましたけどね。

督夫先生 / カンプの十川さんから「模型をもっと一般に理解してもらいたい」という話が出て、「東急ハンズの模型屋さんで展示してもらえないかな」という話になり、早速営業から問い合わせしたら、たまたま東急ハンズの上にギャラリーがあって、そこを閉めてしまうようで空いてるから「そこを使ったらどうだ」と言われ、使わせてもらったのがタミヤモデラーズギャラリーの始まりなんですね。
渋谷の駅から東急ハンズまで、行列という程ではないのですけど「これはモデラーズギャラリーに行く人だな」という流れというか列が分かりましたね。
それまでは百貨店でやらせて欲しいと申請しても「机の上に白い布敷いてその上に戦車とか船並べるなんて百貨店では出来ない」と言う話だったのですが、東急ハンズでやった実績のおかげで、その後札幌そごうでOKが出て「これだったらやっても良い」という事になって、それがギャラリーの1回目だったんですけど。それは嬉しかったですよね。
それから大阪、名古屋、福岡、新潟と全国的に開催していった訳ですね。ですから、ギャラリーのスタートっていうのは十川さんのアドバイスがきっかけになっています。
督夫先生 / 1967年の1月に『タミヤニュース』の第1号を隔月で発行しました。それで、その年の8月に『ジュニアニュース』を出しました。
金子 / ちょっとお聞きしてもよろしいですか?
督夫先生 / はい。
金子 / 松井さんとよく話しているのですが、この前もちょっと俊作社長にお聞きしたんですけども、『タミヤニュース』の第1号が1967年の1月号という形になっていて、今まで色々な出版物とか記録を見ると「1月号」と書かれているので、1967年の1月発行という風に言われているんですけども、どうなんでしょうか?
督夫先生 / 早め早めに原稿作って、そういう物って発売を予定した日より前に発行するという慣例がありますから、それは前の年だと思います。
金子 / そうすると、やはり1966年の12月なり、11月の可能性があると。
督夫先生 / そういう事ですね。

※2008年3月26日 青山のアトリエにて
--- 田宮督夫先生を忍んで ---
田宮督夫先生には、月刊『モデルアート』をはじめとする弊社刊行物の表紙デザイン監修にお力添えをいただきました。そのご指導は私たちにとって大きな学びとなり、先生の卓越した感性と温かなご指導に心より感謝申し上げます。田宮督夫先生を偲んで、謹んでご冥福をお祈りいたします。
なお、本記事は2008年に発行された『パンツァーグラフ!』Vol.12に掲載された、金子辰也編集長によるインタビュー記事「ツインスターを創った男」を再録したものです。より多くのファンの皆様にご一読いただきたく、ここに再掲載いたします。
有限会社モデルアート社 一同